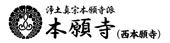「物語」で読み解く仏教 第1話 「老僧の年隠したる事」前半—『季刊せいてん』より

rousou-2「物語」で読み解く仏教 第1話 「老僧の年隠したる事」
『季刊せいてん』106号掲載 龍谷大学准教授 野呂 靖(のろ・せい)
今号から始まりました、「物語」を通して仏教の教えに触れる連載、「〈物語〉で読み解く仏教」。タイトルを見ただけも面白そうな雰囲気が伝わってきますね。
親しみやすい「物語」に浸りながら、自然に仏教の考え方が身につく。そんな楽しい仏教入門になるのではないかと、私ども編集室も楽しみにしています。
ご執筆いただくのは、注目の若手仏教研究者・野呂靖先生です。
さあ早速、物語の世界へ向かいましょう。
イントロダクション
—はじめて仏教を学ぶには—
「先生、はじめて仏教を学ぶのに何を読んだらいいですか?」
学生さんからよく尋ねられる質問です。私はいつも「うーん」と唸(うな)ってしまいます。もちろん、仏教の教義や歴史を明快かつ平易に説明している優れた入門書はたくさんあります。とくにこの10年ほど、出版界は仏教書ブームと呼ばれるほどの活況を呈しており、書店には硬軟とりまぜて多くの書籍が並んでいます。それだけに選択肢が多すぎて、何を選んで良いのかわからないというのが現代の私達の贅沢(ぜいたく)な悩みなのかもしれません。
ただ、わかりやすく書かれた入門書を読めば仏教が「わかる」かといわれると、決してそうではないと思います。入門書はその性格上、込み入った教義・思想をそのまま解説するわけにはいきません。経典の文章の全体を示すわけにもいきません。いきおいシンプルな叙述になりがちです。その結果、釈尊(しゃくそん)や祖師たちによる語り口の魅力が十分に伝えられないという短所があるように思います。
実は仏教の思想をきちんと理解しようとするには、文献そのもの、つまり経典や論書・注釈書などのお聖教(しょうぎょう)そのものにじっくり向き合うのが一番です。多少難しい言葉に出会っても、辞典を引きながら「うんうん」うなりながら向き合ってみる。お聖教そのものが伝える生(なま)のメッセージを感じてみる。
そうすると一見、難解そうにみえた経文の奥底から2500年の時を超え、釈尊や祖師たちが語りかけてくる瞬間が訪れる……はずです。もっとも、現代に生きる私達がいきなり仏典に取り組んでも、「難しい」という印象だけを残して仏教嫌いになってしまう危険性もあるでしょう。
そこでこの連載では、現代の入門書とお聖教とのちょうど中間地点に位置する物語文学を題材に仏教の基礎を読み解いてみたいと思います。よく知られているように、日本では古代・中世を通じて『今昔物語集』に代表される多くの説話集が編まれました。そのなかには、無常や無我、四苦や四諦八正道(したいはっしょうどう)といった仏教の基本思想が、たんに教科書的に解説されるのではなく、僧侶や貴族あるいは妖怪など具体的な登場人物の姿を通して生き生きと語られているのです。
さあ、これから何回かに分けて、物語に描かれた人々の姿を道しるべにしながら「生きた仏教」の世界に分け入ってみましょう。
—年齢を隠した老僧
まずは次の説話から始めましょう。
武州(ぶしゅう)に西王(さいおう)の阿闍梨(あじゃり)という僧がいた。「お年はいくつにおなりですか」と人が尋ねたところ、「60には余ります」と答えるが、七十過ぎには見えたので、疑わしく思えて、「60にどれほど余っておいでか」と尋ねると、「14余っております」と答えた。
余りすぎであった。70と言うより、60と言うと、少し若やいだ気持ちになるため、こう答えたのだった。人の心の常である。お世辞でも、「お年よりずっと若くお見えになります」と言われるのは、嬉しいものだし、「ひどく老けてお見えだ」と言われるのは、心細く残念なのは、誰しも同じである。
(「老僧の年隠したる事」『沙石集』巻八・『新編日本古典文学全集』、418頁)
これは鎌倉時代後期の僧、無住(むじゅう)(1226~1312)が著した仏教説話集『沙石集(しゃせきしゅう)』に収められた一篇です。「老僧の年隠したる事」というタイトルがついています。武蔵国(むさしのくに)(現在の埼玉・東京・神奈川の一部)の老僧が10歳以上もサバをよんでいたというお話。「余りすぎであった」という無住の冷静な指摘が光ります。

鎌倉時代の人々の平均寿命は現代とくらべてきわめて短く、およそ30歳前後だったといわれています。そのなかで70歳を超えるご高齢ですから、むしろ年齢を誇ってもよいようにも思われますが「まだまだ若く見られたい」というのでしょう。「人の心の常である」と述べられるように、「少しでも若く見られたい」という気持ちは現代にも通じるもので、決して他人事ではありません。
—無常と執着
さて、このお話。たんなる笑い話ではありません。二つの重要な教えを伝えています。
一つは「執着」です。
老僧の「若く見られたい」という欲望のことを仏教では執着(しゅうじゃく)といいます。執着とは事物に固執することを指しますが、詳しくいえば「決して変わることのない自我が存在する」と考え執着してしまう我執(がしゅう)と、「すべての存在に実体がある」と考える法執(ほうしゅう)に分けられます。このうち、我執とは要するに「自分自身に対する執着」であり、これこそが「いつまでも若く、変わることのない自分」にとらわれてしまうことなのです。
仏教では、この「我執」のはたらきが根本となってさまざまな煩悩(ぼんのう)が生じ、いつまでも迷いの世界にとどまってしまうと考えます。ですから、一刻も早く「我執」を絶たなければいけません。無住は次のように続けています。
人の身は、父母の精を受け、地水火風(ちすいかふう)の四大(しだい)が一時的に集まってできたものである。…この中に、自ら頼みとできるものはない。心こそ我が物というべきだが、妄心は妄境を原因として生じ、刻々と変り、消えていく。一瞬一瞬に生じては消え、瞬時も留(とど)まるところがない。身も心も頼みにできるものはない。(同、419~420ページ)
きわめて的確な説明です。自分の心と体は一瞬一瞬変化するものであって、決して確かな依(よ)り所にはなりえません。しかし、私たちはこの必ず変化してしまうという無常の道理をなかなか受け容(い)れられません。歳を取りたくないし、病気にもなりたくない、そしていずれ訪れる死こそ最も恐ろしいものです。
仏教はこうした無常の道理と「変わりたくない」という私たちの「執着」との間に生じたギャップこそが、苦しみの最大の原因であると説いています。無住は移ろいやすい無常なる世界のなかで執着を持って生きる私たちに対し、「よくよく無常の道理を知りて、常住の仏法を尋ぬべし」(同、422ページ)と語りかけています。
もう一つ、このお話で大事なポイントは「執着の絶ち難さ」です。この老僧は阿闍梨とよばれていました。阿闍梨とは、そもそも弟子を教え導く「師」のことで、日本ではとくに天台宗や真言宗において灌頂(かんじょう)を受けた官職をさしています。したがって、この老僧は弟子をとるまでに仏道を歩み、多くの人生経験を積んだ僧侶であったはずです。ところが、「若くみられたい」という一見取るに足りないような執着からでさえ逃れられていません。
無住は密教の教えを学びながら西大寺流(さいだいじりゅう)の戒律を受けており、晩年には禅門にも身を投じています。まさに諸宗の教えを幅広く学び、諸行を実践していく立場でした。しかし、煩悩を厭(いと)い離れる道を歩みつつも、いっぽうで「人間の余執(よしゅう)(心に残っている執着)はなくなり難い」と語るなど、人間の持つ絶望的なまでの執着の強さを認めています。無住はこの老僧に仏道を歩むことの困難さを実感する自分自身の姿を重ねていたのかもしれません。
季刊せいてんについて

その他の『季刊せいてん』の年間購読はこちら!
本願寺出版社
季刊せいてん
●季刊 年4回発行(3月・6月・9月・12月の各1日) B5判
「季刊せいてん」 は、はじめて 「浄土真宗聖典」を手にする方にも、わかりやすく学習・聞法していただくことができる味わい深い聖典学習誌です。創刊号より次のような編集方針で発刊をつづけています。
■現代人の「ことば」で語る
■聖典が、とにかく身近になる
■続けて読んで、そして深まる
■グループ学習に最適のテキスト
■随所に読みやすさを工夫
編集/浄土真宗本願寺派 総合研究所
発行/浄土真宗本願寺派 本願寺出版社
季刊せいてん No.106 2014春の号より転載
著者:浄土真宗本願寺派 総合研究所
判型:B5判
定価:¥700(本体¥649+税)
※売り切れの号もございます。