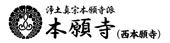「他力本願」の誤用を、どう考えればよいのか

社会の変容、時代の流れと共に言葉の解釈にも変化が生じることがありますが、仏教語も例外ではないようです。特に浄土真宗では、「他力本願」という言葉の誤用が、近年たびたび取り沙汰されていますが、これはどのように考えれば良いのでしょうか。
浄土真宗の教えやその用語には誤解を招きかねないものがたくさんあります。例えば『歎異抄』の「善人なおもつて往生(おうじょう)をとぐ、いはんや悪人(あくにん)をや」(833頁)「親鸞は父母(ぶも)の孝養(きょうよう)のためとて、一返にても念仏申したること、いまだ候(そうら)はず」(834頁)等々の法語です。これらの言葉に初めて接した人はびっくりされることでしょう。親鸞聖人という方は、なんと非常識な人であったのかと驚かれる人もいることでしょう。「他力本願(たりきほんがん)」という言葉についても、他人に依存した消極的な考えを示す言葉であると受け止める人も大勢いることでしょう。
私たちは教育やメディアが発達したお陰で、たくさんの知識や情報を手に入れることができるようになりました。コンピューターを駆使すれば、世界中の情報を瞬時に手に入れることができます。しかしそうした知識や情報の大半は処世術(しょせいじゅつ)のための手段です。換言すれば、自分の欲望を満足させるための情報や知識といってもよいでしょう。
一方、浄土真宗の教えやその内容をあらわす用語は、世の中を上手く生きていくための手段となるものではありません。
それではいったい、親鸞聖人は何を求め何を明らかにされたのでしょうか。聖人は29歳の時に20年間修行した比叡山(ひえいざん)を後にし、六角堂に百日間参籠(さんろう)されました。その後、法然上人(ほうねんしょうにん)の元へさらに百日間通われています。
『恵信尼消息(えしんにしょうそく)』によれば「生死(しょうじ)出づべき道」(811頁)を求めてのことであったと記されています。「生死出づべき道」とは、私たちが避けて通ることのできない苦悩を解決する道のことをいいます。聖人は当初それを自力(じりき)の道に求められたのです。自力とは、
とあるように、わが身、わが心をたのみとすることをいいます。しかし親鸞聖人にとって問題になったのは、そのたのみとすべき自分自身だったのです。聖人は『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』「仮身土巻(けしんどかん)」に、
と記されています。愚かな凡夫(ぼんぶ)には『観経』に説かれた定善(じょうぜん)の行も、散善(さんぜん)の行も修めることができない。だから、たとえ千年という寿命を費やしても、真実を見る智慧(ちえ)の眼を開くことはできない、というのです。
この愚かな凡夫とは、正(まさ)しく親鸞聖人ご自身の姿だったのではないでしょうか。聖人は自らをあてにした自力修行では、20年という歳月を費やしても、自らの抱えている苦悩の解決、さとりを開くことはできなかったのです。聖人の求道が真剣なものであればあるだけ、自らが歩んできた道では目的は達成されないと分ったときの絶望感は、筆舌(ひつぜつ)に尽くしがたいものがあったと思われます。
そうした絶望の淵(ふち)にあったとき、今度は逆に目指すべきさとりの世界からのはたらきのあることに気づかれたのです。それまではただひたすら、わが身をたのみとして苦悩の解決を図っていたのが、目指すべきさとりの世界からのはたらきによって、たのみとしていた自らの姿がありのままに照らし出され、ありのままの自分がそのままに、そのはたらきによって救われていくことに気づかれたのです。それが法然上人の導きによる他力本願の法との出遇(であ)いだったのです。
バブル景気が崩壊して後、しばらく心の時代ということが新聞紙上等で取り上げられました。欲望を重視した考えからの転換を訴えたものだったのでしょう。しかしながら、自分自身に目を向けることはなかなか難しいようです。私たちの目は、たえず外にばかり向いています。しかも外に向いたその目は、自分の今もっている価値観を信じて疑わない目です。その目を通して見ることにより、自ら苦を生み、他の人も傷つけていることに気付きません。
親鸞聖人は逆にそうした自分自身を問い続けたのです。その結果出遇ったのが、自分自身の姿をありのままに照らし、そのままに救い取って下さる他力本願の法であったのです。
そのような性格の法を、処世術のための手段として受け止め、その範疇(はんちゅう)で理解しようとするところに、混乱を生じる原因があると思われます。
「せいてん質問箱」より転載
(ホームページ用に体裁、ふりがな等を調整しております)
他力本願の意味とは?