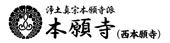宗教人類学でひもとく葬儀の意味|自治医科大学教授 田中大介さんインタビュー<前編>
葬儀無用論を超えて
――そもそも葬儀はなぜ必要なのでしょうか?
田中:葬儀という出来事は要/不要という次元を超えて存在しているものだと思います。もちろん、葬儀の意味・意義・目的・必要性というものを言葉で説明することは可能ですが、どこかの時点でそのような論理性が消え去ってしまうからこそ、「死の文化」として成立していると言えるのかもしれません。
人類学の中でも死者儀礼、葬儀はかつてメインストリームでした。人類学の中でも、より細分化すると儀礼論になり、この分野には膨大な蓄積があります。人々が様々な意味を投げ込むことができるブラックボックスになっているのが儀礼であり、ロジカル、システム化して人々に共有されると、もはやそれは儀礼ではなく別のものになってしまいます。たとえば、なぜ焼香するのか?という問いがあり、そこに対して人々がそれぞれの意味や目的をつくることができるのが儀礼だと思います。
また、いわゆる葬儀無用論に類する論調は過去から連綿と繰り返されてきていますが、葬儀というものはなくならないと考えています。必要・不要という次元を超えているからこそ、変化することはあっても無くなることがないのです。仮に葬儀を行わず、生ごみのように人間の亡骸を捨ててしまうならば、それはもはや人間、社会という存在そのものが消えてしまうことだと思います。人間の文化は、生きている人だけで成立しているものではありません。亡くなった方も含む無数の蓄積も含めて、人間の社会が成り立っています。亡くなった方とのつながりを確認することができることが、弔う、偲ぶ行為だと思います。そこへいろいろな意味づけを付与します。葬儀は、これらの意味づけを排除するのではなく、包み込むものであり、開かれたものであり続けると思います。
――よい葬儀とは何ですか?
田中:「死者も生者も共にある」ということを感じられる機会になる、ということではないでしょうか。それこそが「弔う」あるいは「偲ぶ」ということなのかもしれませんが、さまざまな人びとの思いを柔らかく、そして安らかに包摂できるような葬儀のありかたに、私としては共感を覚えます。同時に、葬儀はよい/わるいという二分法的な考えかたを超えたところにあるという思いも抱いています。
――近年、葬儀に関してどのような変化を感じますか?
田中:葬儀は個人化が進んでいますね。家族(世帯)を構成する人数そのものが減少し、会葬者も減少の一途をたどっています。かつて、葬儀社でフィールドワークを行ったとき、参列者が一人だけの葬儀に立ち会ったことがあります。私が「一人ぼっちで、かわいそうだね。」と若い葬儀社スタッフに語りかけると、意外にも「むしろ、たった一人でも葬儀を行っているなんて、すごいし、えらくないですか。」という返答が返ってきて、なるほどと思いました。
人数の問題ではなく、ご遺族が偲んで、弔って、つながりを確認していることが重要なのです。日本の葬儀における個人化は、利己的な個人化というよりも、「私事化」、つまりプライベートなものとして進行しているものだと私は認識しています。「おひとりさま」という言葉も、この「私事化」の象徴だと思います。葬儀は不特定多数に開かれた出来事であるというよりも、「わたし」を核として、より私事化されたものになっているのです。
インタビューは後編に続きます。
葬儀は“つながり”の結節点│自治医科大学教授 田中大介さんインタビュー<後編>