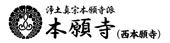「医療者だって死にますよ」異なる当たり前を話すということ|古川潤哉さんインタビュー<後編>
衣を着て、中学校で性教育・思春期支援の活動に関わる古川潤哉さん。
前回に引き続き、その活動について、うかがっていきます。

― お坊さんが中学校のなかに入って、「性教育」に関わる。なかなかできないことだと思うんですが。
実は、実績のある活動グループに紹介されて入ることができているんです。個人の僧侶として単独でやっているわけではないんです。もちろん佐賀でも、僕が突然、学校にコンコンとノックして行っても入れてくれるわけではないですから。
いま佐賀県の中学校で行っている性教育の授業は、「佐賀県DV総合対策センター」がつくっている3年間通したDV予防プログラムのなかの一つなんです。私の講義が、独立してそれ一つで完結しているわけではなくて、婦人科の先生の話、デートDVの話、携帯電話の使い方の話、コミュニケーションの話があったりする中の一コマとしてあるんです。
お坊さんが衣をきて、性教育、セクシャルな話をするっていうところに目が行きがちだけれど、実際はネットワークの中で、行政、お医者さん、学校、専門家のネットワークのなかでやっています。
―すごく、目がひらかれました。単独ではなく、ネットワークの中、網の目の中の一つとしての立ち位置でされているわけですね。
もともとは、佐賀でHIVのことをやっているときに、岩室紳也先生という横浜の先生と、学校性教育、思春期支援の分野で知り合いまして、横浜で毎年開かれている「AIDS文化フォーラム」というイベントに招いていただくようになりました。「宗教とエイズ」というようなセッションを持たせて頂くようになったことから、それで佐賀でもやりやすくなったんです。
今は佐賀大学医学部の入学時のオリエンテーションで一時間コマをもらっているんですが、そこでしている話で、みんなが驚くのは、「医療者だって死にますよ」という話なんです。
みんな、高校や予備校でがんばって、医療者として「人の命を救いたい!」という思いで入ってくるんですけど、医療者が死なないわけじゃない。目の前の患者さんを治療できたとしても、病気が治ったからといってその人が死ななくなるわけじゃない。
そんなことを講義でいうと、みんなちょっとショックを受けるわけです。けれども、仏教者からみると、じつはそれは当たり前なんですね。そういう視点の違いに、いままで、医療の現場とかで活動してこられた方が、「なるほど」といってくださったり、今まで腑に落ちなかったところがそれで解決がついたと言われたりということがあります。
―僧侶と、医療従事者、お互いの当たり前がちがう。
僕らと関わってくれる医療者とか、思春期支援をされている方たちは、問題意識が多くって、今のやり方ではどうもならないと考えている方がたくさんいます。現代のいろいろな課題に対して、答えの出る問題ではないことについて、宗教者が問い、発言をして欲しい、宗教者に関わって欲しいと思ってくださっているかたがたくさんいます。しかし、僕ら宗教者の方が、その関わり方をよく知らない。とっかかりがないという問題を持っている。
それから、たとえば、思春期支援だといって、お坊さんが突然でかけていって話をすると、当事者の持っている現場の問題意識とか、なにが問題なのかよくわからないまま話すと、頭ごなしになって、あぶないんですよね。根性論をいってしまったりとか。
いま問題になっているのは、自分の思春期時代を思い返して話すことではなくて、今の子どもたち、「今の思春期」ですからね。自分の経験がある分むずかしいんですけれど、今の子どもたち、今の思春期というのを理解して関わらないといけない。
お坊さんだから、死の問題、思春期でも、目の覚めるようなことを言えるような意識があるかもしれません。しかし、本当に有意義な関わりをしようとするならば、その現場の当事者の想いや、問題・関心をちゃんと理解しておかないと、ずれたり、響かなかったり、あるいは傷つけたりということが起こるんです。

―最後に今後の展望があれば。
いまの、お坊さんとして、思春期支援等の活動に関わるというのは、狙ったわけではなく、役回りとして、結果的にこうなったと思っています。結果的にオリジナリティのあるポジションになっていますが、みんなでやれたほうがいいんです。研修プログラムがあって、関心がある方は受講すればみんな関われるようになるというのが理想です。研修を受けたお坊さんが、それぞれ自分の地域に戻って、既に活動されている市民の思春期支援ネットワークに紹介されていくようなシステムもあっていいと思います。将来的には、宗派でのキッズサンガの取り組みの延長線上にそういう仕組みができたら生きづらさを抱えている若い人の一助となれるのではないかと考えています。