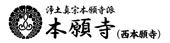「御布施(お布施)」にはどういう意味が?【仏事の疑問】
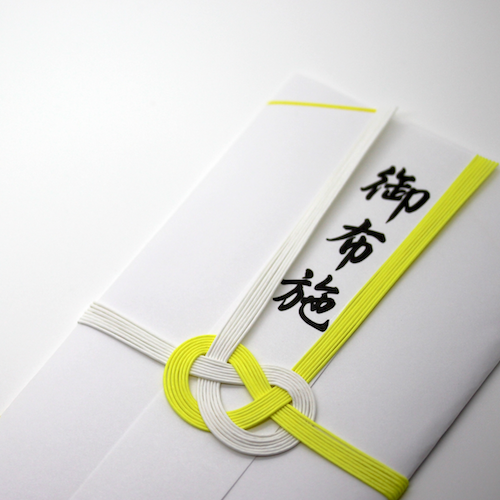
「御布施」にはどういう意味が?
(『せいてん質問箱』より)
Photo:写真AC
葬儀や法事の時にご住職に渡す金封に「御布施」と書きますが、この「布施」にはどういう意味があるのでしょうか?
布施という言葉
「布施」の「布」は、もともと「ぬの」の意味ですが、「ぬの」は敷き広げられるものです。転じて、「布」は「ゆきわたらせる」「ほどこす」という意味を持つようになります。つまり「布施」は、「布」も「施」もほどこすという意味なのです。
「布施」の原語は、インドの「ダーナ」という言葉です。「ダーナ」は「与えること」という意味ですので、漢訳は元の意味を忠実に翻訳していると言えます。
布施の歴史
さて、インドには、お釈迦(しゃか)さまが仏教をひらかれる以前から、出家修行者に対して食べ物などを施す習慣がありました。たとえば、修行者であったお釈迦さまは、厳しい苦行をやめた後、近くの村の娘スジャーターさんから乳粥(ちちがゆ)を施与されたと伝えられています。お釈迦さまはこの乳粥によって体力を回復され、菩提樹(ぼだいじゅ)の下で瞑想(めいそう)に入り、さとりをひらかれます。このスジャーターさんの乳粥を施すという行為が、まさしく「布施」であります。
布施の目的
それでは、なぜ出家者に対して布施が行われるのでしょうか。元来インドでは、功徳(くどく)を積んだ出家者に対して布施を行うことで、功徳が分与(ぶんよ)されると考えられていました。布施によって功徳の恩恵にあずかり、その結果、天に生れることができると考えられていたのです。
また、布施を頂戴する出家者が布施をなした者に対して教えを説くという習慣もあったようです。
このような、出家者が教えを伝え、それを在家者が喜ぶという関係があったことも、出家者を布施という形で支えるインド社会の形成に寄与したと考えられます。
仏教の布施の分類
仏教では、布施を財施(ざいせ)と法施(ほうせ)の二種類に分類するようになります。また、この二種類に人々から恐れを取り除く無畏施(むいせ)を加えて三種類に分類することもあります(一五三一頁)。
財施とは文字通り食べ物などの生活の資財を布施することです。法施とは、出家者が在家者に教えを説くことです。先にも述べたように、インドには教えを説くという習慣が、古くから根付いていました。それが布施の―つに分類されるようになるのです。
このように、教えの伝達を布施とするようになることも、仏教における布施の重要な特徴と言えます。
無財の七施
法施の例からもわかるように、布施の意味は財物の授受だけに限られません。
『雑宝蔵経(ぞうほうぞうきょう)』には有名な「無財(むざい)の七施(しちせ)」が説かれます。七施は、眼施(げんせ)・和眼悦色施(わげんえつしきせ)・言辞施(ごんじせ)・身施(しんせ)・心施(しんせ)・床座施(しょうざせ)・房舎施(ぼうしゃせ)の七つです。それぞれ、やさしいまなざしで接すること、しかめっつらをせず、良い表情で対応すること、優しい言葉をかけること、きちんと挨拶(あいさつ)すること、心を込めてふるまうこと、すわる場所を設けること、部屋を使ってもらうことを意味しています。
また、『優婆塞戒経(うばそくかいきょう)』には、暑いときには扇(あお)ぎ、着物で陰を作り、寒いときには火をたいてやり、また着物であたためてやり、盲目の人がいれば手を取り杖(つえ)を取って導く、といった布施の方法も示されています。
布施のこころ
「無財の七施」や『優婆塞戒経』にも見受けられるように、布施は、心のありようとも深く関係しています。たとえば、見返りを期待して布施を行ったり、何らかの行為の返礼と考えて布施をしてはならないとされます。布施は貪(むさぼ)りのない気持でなされることによって、行為に価値が生れるのです。ですから、「読経料(どきょうりょう)」「御経料」といった表現は、読経の代金を意味しているように受け取られるので、「御布施」を包む時には、ふさわしくないと言えます。
布施波羅蜜
大乗(だいじょう)仏教の基本的な行法に、六波羅蜜(ろっぱらみつ)があります。
この中に、布施は「布施波羅蜜(ふせはらみつ)」として組み込まれます。布施波羅蜜とは「極限まで布施をなすこと」を意味していますので、決して容易な修行法ではありません。
具体的には、六波羅蜜の修行は般若波羅蜜を基調としており、たとえば『金剛般若経(こんごうはんにゃきょう)』は、布施を行う時には、布施をなす者、受け取る者、施される、物の三つを空と見なくてはならないと厳しく戒(いまし)めます。つまり、諸存在が固定的な実体をもたないこと、即ち空であるという智慧(ちえ)に基づいて、行じなければならないのです。そして、空であると知ることによって、執着(しゅうじゃく)が完全に断たれ、布施波羅蜜は、行(ぎょう)として成立するのです。このように、布施波羅蜜は、行ずる主体の内面─心のありよう─が重視される行なのです。
浄土真宗の布施
仏教における布施の意味を振り返りながら、浄土真宗の布施について考えてみましょう。元来布施は、天に生れるという基本的な目的を持つ一方で、教えを伝え、それを喜ぶ心と関係していました。また、仏教では教えを伝えることも布施の一つとされるようになります。更に布施は、それを行う心が重視されます。その行者の内面が重視され、厳格な修行となったのが大乗仏教における布施波羅蜜です。
このように布施は、長い歴史の中で変化してきました。
さて、浄土真宗における布施ですが、『唯信紗(ゆいしんしょう)』に、布施による往生は、自力諸行(じりきしょぎょう)の往生と規定されています(一三三八頁)。このことから確認できるように、布施波羅蜜は私たち凡夫(ぼんぶ)の成し遂げられない行業(ぎょうごう)であり、浄土真宗が、布施によってさとりを目指していないことは言うまでもありません。布施の歴史の中で考えるならば、やはり、教えが伝わり、その教えを喜ぶという伝統を受け継いだものが浄土真宗の布施と言えるでしょう。
身近な方の死をご縁として阿弥陀如来の救いに出遇(であ)い、その出遇えた喜びを分かち合いたいという思いが、浄土真宗の「布施」という言菓の中に結実していると、受けとめることができようかと思います。
教学伝道研究センター常任研究員(現 浄土真宗本願寺派総合研究所 副所長)
藤丸智雄
※写真はイメージです。