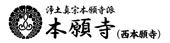宗教は、行政・企業が救えない人々のセーフティネットに|赤堀正卓さん(『終活読本ソナエ』元編集長)インタビュー<後編>
安易な終活は、かえって絆を断ち切ってしまう
ーー2013年の『ソナエ』創刊時から2022年の休刊まで、終活はどのように変化しましたか? また、今後はどうなっていくとお考えですか?
赤堀:「終活」の認知度はかなり高まりました。『ソナエ』創刊当初は「エッジが効いた雑誌だね」と、言われましたが、最近は定着してきました。
心配なのは、終活情報が溢れかえるようになったことです。終活なんてしなくて、自分の死を周囲の人に委ねてしまえばいい人たちも、終活をすることに迫られてきてしまったような雰囲気があります。
「迷惑をかけたくない」という思いは根強いのですが、それをそのまま実行してしまうと後で問題になる場合があります。専門家を頼って終活のさまざまな手続きを進め過ぎてしまうと、肉親との絆を切ってしまうことにもなりかねません。たとえば公正証書や遺言をつくってしまうと、かえって親子の摩擦が生まれてしまう場合があります。
エンディングノートを書いている過程で、頼れる親戚の存在に気づくなど、自分を取り巻く関係性が見えてくることもあります。あるいは生前墓を探すなかで「墓友」ができる場合もあります。そうした絆のつくり直しこそが大切なのです。

相続、葬儀、健康などのセミナーも開催された(2017年・大阪)(写真提供:産経新聞社)
ーー終活に関して、お寺にできることは何でしょうか?
赤堀:葬儀やお墓、あるいは死について、ここ数百年で当事者に一番近くにいたのはお寺や僧侶だと思います。もしかすると、そこに甘んじてしまっていた部分もあるのではないでしょうか。人の死と向き合うのであれば、何のために葬儀を行い、どのように故人を見送るのか、遺された方のグリーフケアをどうするのか、家の継承の意味は何か、など、もう一度問い直していただきたいと思います。
葬儀とは距離を置き、独自の道を突き詰めていくお寺があってもよいと思います。
お寺が持つ、企業には無い強みは、資本主義ではなくてもやっていけるということです。
宗教家を志すのであれば、経済的には貧しくても心が豊かな方がもっと増えるとよいと思います。私は、宗教は社会のセーフティネットだと思っています。終活においても、行政や企業が救えない所得が低い層にアプローチすることができるのではないでしょうか。

雑誌だけでなく週1回のラジオ番組出演(ラジオ大阪『終活ラジオソナエ』)にも出演(写真提供:産経新聞社)
ーー今後の展望をお聞かせください。
赤堀:『ソナエ』はおかげさまで9年間継続することができ、部数や売り上げも堅調で、心強い人脈も残りました。しかし、社内の事情で一旦休刊することになりました。
とはいえ今後取り組みたい、関心のあるテーマはあります。近年、終活サービスを享受できない低所得者層に対して、行政が支援に乗り出しています。よからぬベンチャーに荒らされる前に、地域の伝統的な葬儀社さんや墓石屋さんと一緒に支援に取り組んだ方がよいのではないかと思います。そのあたりの課題に対して、何か私にできることを考え、応援をしていければと思っています。
ーーありがとうございました。
プロフィール
赤堀正卓(あかほり まさたか)さん
『終活読本ソナエ』元編集長
1968年生、静岡県出身。
1991年に産経新聞社に入社。主に社会部に所属して、司法、都庁、厚労省、法務省、宗教面などを担当。副編集長兼社会部デスクを経て、2013年に社内ベンチャーとして『終活読本ソナエ』を立ち上げ。
2022年現在、産経新聞出版・専務取締役。