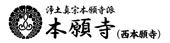生きている人と亡くなった人がともにすごせる場を|五藤広海さんインタビュー<後編>

地元でのグリーフケア活動の活動紹介(画像提供:五藤さん)
「これなら僕も、悲しんでいる人に関わっていけるかもしれないと思えたんです」
浄土真宗本願寺派の寺院・光蓮寺に生まれ、生きづらさを感じながら子ども時代を過ごし、出会いと別れの経験のなかで僧侶の道を志した五藤広海(ごとう・ひろみ)さん。僧侶としての活動を始めてからも、他者との関係や別れの場での自分の無力さに悩まれたといいます。
後編となる本記事では、そうした五藤さんが「グリーフケア」との出会いをきっかけに、どのように他者との接し方を得て、そして地域での活動を始められたのかを伺いました。
お寺生まれの音楽少年が、浄土真宗の僧侶になる旅路|五藤広海さんインタビュー<前編>
グリーフケアとの出会い
――僧侶としてご活動をはじめられて、どのようなことに悩まれましたか。
五藤広海さん(以下 五藤):最初は苦悩ばかりでしたね。悲しんでいるご遺族にどのように関わって行けば良いのか。一緒に悲しむべきなのか。それとも儀礼の役割に徹するべきなのか。声はかけるべきなのか。かけるならどんなことから始めるのか。何一つ分かりませんでしたから。

お寺で開催している大切な人を亡くした人の場「こころの教室」(画像提供:五藤さん)
――お葬儀での作法はわかっても、具体的にどうしていくべきなのかについて蓄積が無かったんですね。
五藤:そうですね。そんな状況で、松本紹圭(まつもと・しょうけい)さんが主催される寺院運営の学びの場である「未来の住職塾」に二期生として参加していたんですが、卒業式で一般社団法人リヴオン代表の尾角光美(おかく・てるみ)さんの公演をお聞きしたんですね。そこではじめて「グリーフケア」という言葉に出会って。とても衝撃的でした。どうして今までこれに出会ってこなかったんだろうと、怒りすら感じるほどでしたね。
そこでは、大事な誰かを亡くしたときにどんな反応が起きるか、きちんと学問として体系づけられていて。たとえば僕や母が認知症の祖母を亡くしたときに、悲しいだけではなくほっとしてしまった面があることもおかしなことではなくて、十分にあり得る「自然」なこととして説明されていました。そうしたお話を聞くうちに、これなら僕も、悲しんでいる人に関わっていけるかもしれないと思えたんです。
そこからリヴオンで「グリーフ」や「グリーフケア」に関する学びの時間を何年かとって、そのうち「いのちの学校」「僧侶のためのグリーフケア連続講座」など、伝える側として、発信の活動を手伝わせていただくようになりました。
――「グリーフケア」ということは、別離の悲しみを抱えておられる方へのケアを中心に学ばれたのでしょうか。
五藤:これはあくまでも僕から見たところになりますが、「グリーフケア」という言葉で誤解されやすいのは、これは誰かをケア出来るようにするためのものではない、というところです。こうした面ではもしかしたら「グリーフケア」より「グリーフ」と表現する方が適切なのかもしれません。
他者にケアを与えるのではなく、自分の中にある喪失体験を見つめたうえで、それを共通項に他者とどんな風に関わっていくのかを学ぶのが「グリーフケア」だと思っています。お寺にいて分かるのは人間大小なにか喪失しながら生きているということです。なにかを喪失した人とどう関わっていくのかを考えたとき、自分の中の喪失体験がそのヒントになるんです。
――なるほど。あくまでも自分の喪失体験との関係が主となるんですね。
五藤:僕はちょうどグリーフについて学んでいる時期に離婚を経験して、この喪失はとても大きな喪失なんだ、と感じました。それこそ、人生が終わってしまったと感じるくらいに。眠れなくなったり、食べすぎてしまったり、心身にでた影響を、きっとこれは他のかたも同じ体験をしていくんだな、と思えるようになって。だからこそ、葬儀の場でもご遺族に対して「夜眠れていますか?」とか「お食事は出来ていますか?」といった言葉が自然に出てくるようになっていきました。自分の中の別離や痛みを見ていくことが、他者とのつながりを産んでいく。こうしたグリーフケアのあり方は、仏教と親和性があるように思っています。