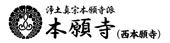お焼香の意味は何ですか?【仏事の疑問】

お焼香の意味は何ですか?(『せいてん質問箱』より)
法事にお香を焚いたり焼香するのはなぜですか?
インドの香文化と仏教
世界の様々な地域で古くから用いられてきたお香は、宗教的な意味を持つことも多いようです。とりわけインドにおけるお香の歴史は古く、仏教以前の古代の文献にも、お香についての記述が見られます。このように、お香と関わりの深い文化の地インドで生れた仏教は、その当初より、お香と密接な関係を持っていました。
釈尊(しゃくそん)のご遺体が栴檀(せんだん)という香木で造られた棺におさめられ、周囲を香木で覆い、香油(こうゆ)を注がれ火葬されたと伝えられているのも、その一例と言えるでしょう。
仏教とお香の伝播
お香の文化は、仏教とともに中国へ、更に日本へと伝播(でんぱ)しました。日本にお香が伝わったのは、仏教伝来(五三八年頃)とほぼ同じ時期と推測されています。古くは『日本書紀(にほんしょき)』推古天皇(すいこてんのう)三年(五九五)に、淡路島(あわじしま)に沈香(じんこう)が漂着し、それを沈香と知らず鼈(かまど)にくべたところ、芳香が立ちのぼり、驚いた島民が天皇に献上したという記録が残っています。まだ仏教伝来間もない頃であり、日本では産出されないお香についての惜報は乏しい状況だったでしょうから、さぞや大きな驚きであったでしょう。
仏教とともに日本に定着していったお香は、次第に日本独自の展開を見せるようになり、平安時代には貴族の生活や遊びの中に取り入れられ、文学作品の中にも登場するようになります。更に、室町時代になると、茶道・華道とともに香道が三道を形成することとなります。現在では、お香の原料は、化粧品やアロマテラピーなどにも使用され、一層幅広く豊かな文化を生み出しています。
お香の種類
お香は、まず原料によって大きく動物系と植物系に分類されます。動物系には、雄の麝香鹿(じゃこうじか)から産する麝香、抹香鯨(まっこうくじら)の胎内で形成される竜涎香(りゅうぜんこう)などがあります。植物から得られるものは、白檀(びゃくだん)、丁字(ちょうじ)、茴香(ういきょう・はっかく)、桂皮(けいひ・シナモン)など数多くあります。
仏典に多く出てくるものとしては、ベトナムを原産地とする沈香があります。
ジンチョウゲ科の常緑樹の樹脂が木の中で凝固したもので、成熟すると水に入れても浮かばないため沈香と呼ばれます。この沈香の良質なものが伽羅(きゃら)として珍重され、正倉院(しょうそういん)には長さ一・五メートル、重さ十一キロ余りの「蘭奢待(らんじゃたい)」という銘の伽羅が収蔵されています(この銘には「東大寺」の文字が隠されています)。また、栴檀も仏典にしばしば登場する代表的な香木です。『大経(だいきょう)』には仏名や浄土にある樹木として、『安楽集(あんらくしゅう)』には念仏の不可思議なはたらきの譬喩(ひゆ)として説かれています。
栴檀は薬用としても用いられたようで、『華厳経(けごんぎょう)』等には匂いによって病が癒えたと説かれています。
お香は形状と用法によっても分類されます。香料を細かく刻み、調合したものは焼香に用いられます。また、粉末状にした抹香(まっこう)は、仏像に散ずる時や、お香を長くくゆらせるための常香盤(じょうこうばん)、時間を計る時香盤(じこうばん)等に用いられます。更に細かく粒子状にしたものは、手や額に塗りつける塗香(ずこう)として使用されます。
一般に広く使用されている線香は、香りを長く保っために工夫されたもので、日本でも江戸時代初期には製造されるようになっていたようです。
長短により燃焼時間が変るので、坐禅(ざぜん)などの時間を計ることにも用いられます。なお、本願寺派では線香は香炉(こうろ)に寝かせて使用します。
仏典の中のお香
仏典の中に説かれるお香について見ていきながら、仏教でお香が用いられる意味を尋ねてみましょう。
まず、お香は良い香りをたてながら煙となって立ちのぼっていきます。このようなお香の性質から、仏を招来する使いと考えられ、法要などにおいて用いられたようです。またお香の香りは、悪い臭いを除きます。経典を手にしたり仏像に向かう時には、つつしみの心から香を焚きしめたようです。
もちろん、天親菩薩(てんじんぼさつ)の『浄土論(じょうどろん)』に「天(てん)の楽(がく)と華(け)と衣(え)と妙香等(みょうこうとう)とを雨(あめふ)らして供養(くよう)し、諸仏(しょぶつ)の功徳(くどく)を讃(さん)ずるに、分別(ふんべつ)の心(しん)あることなし」(七祖三二頁)とあるように、仏典では供養の具として最も多く登場します。しかし「必ずしもお香で供養して仏恩(ぶっとん)に報いることだけが報恩(ほうおん)ではない。
経典を読誦(どくじゅ)し、教えを聞くことが何よりの供蓑になるのだ」(『大般涅槃経』だいはつねはんぎょう)と釈尊が仰っていることや、『大経』中輩段(ちゅうはいだん)に焼香の功徳による願生(がんじょう)が説かれますが、浄土真宗では、念仏一つによって往生が成就するとされていることなども注意されねばなりません。
お香は譬喩としても仏典に説かれます。お香の香りは、しばらく私たちの体や衣服に残り香となってとどまります。この性質から、戒香(かいこう)、施香(せこう)といったように、修行の功徳が身に付いていくことの喩えとして用いられます。
また、お香の香りは移り香ともなります。この性質から、功徳を持つ仏菩薩等のはたらきが、人々に影響を与えていくことの譬喩としても使用されます。
親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、『浄上和讃』に「染香人(ぜんこうにん)のその身には香気(こうけ)あるがごとくなり これをすなはちなづけてぞ香光荘厳(こうこうしょうごん)とまうすなる」(五七七頁)と示され、念仏するべくもない私たちが念仏を喜ぶ身となるのは、阿弥陀如来が私のところではたらいてくださっているからであることを、お香の移り香に喩えて教示されています。
お香の馥郁(ふくいく)たる香りが私たちを包み込み、私たちの香りとなっていくことの中に、摂取不捨(せっしゅふしゃ)のはたらきに包まれ、念仏するわが身が重なり合って惑ぜられたのでありましょう。
おわりに
仏典の中ではお香は、ほとんどの場合「嗅ぐ」ではなく「聞く」と表現されます。このことからもわかるように、お香は嗅覚に惑受されるだけでなく、その香りから多くのことが感じられ想像され意味が見出されるものです。仏典にも、お香について本稿に紹介しきれない程多くの意味が説かれています。お香の豊かな香りに託された多くの仏教者、念仏者の思いを尋ねていくと、そこには仏教の豊かな歴史が広がっています。
教学伝道研究センター常任研究員(現 浄土真宗本願寺派総合研究所 副所長)
藤丸智雄