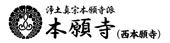宗教人類学でひもとく葬儀の意味|自治医科大学教授 田中大介さんインタビュー<前編>

「葬式は要らない」。葬儀のあり方を考えるとき、少なからず葬儀無用論も叫ばれます。しかし太古の昔、ネアンデルタール人の時点で既に葬儀の萌芽はあったとされ、時代を越えて葬儀が行われてきたことも事実です。今回は宗教人類学者である田中大介(たなか・だいすけ)さんをお招きし、葬儀本来の意味や、それを営む人間の本質について、お話をうかがいました。
商社マンから宗教人類学者に転身
――主な研究テーマは何ですか?
田中大介さん(以下:田中):宗教人類学です。大きな枠組みとしては「人間が死ぬときのありかた」が研究対象になりますが、より具体的には現代の日本における葬儀の文化的動向をテーマとしています。ただし葬儀といっても葬送儀礼に限らず、「葬制」すなわち死と死者の発生をめぐる慣習や習俗全体が調査研究の対象です。
――なぜ会社員から研究の道に進まれたのですか?
田中:幼い頃、地獄絵図を見たときに、自分が死んだ後の行く末が怖かったですし、死というものを身近に感じていました。また、私が5歳のときに父が他界し、会社員になってすぐに祖母が他界しました。そのような経験もあったため、人間が死ぬということはどういうことなのか、昔から考えていました。死や生と向き合い、ライフワークとして研究したいと漠然と考えていました。就職先としては商社を選び、働くのは好きでしたが、人類学の大学院に通うことにしました。ハードワークをこなしながら、入試のときに、それまで書いたことがない人類学の論文をなんとか書ききって提出しました。会社の昼休みに合格発表を見て、すぐに上司に合格を伝え、入学後に退職しました。今考えると無謀な挑戦だったかもしれません。
人類学はフィールドワークが基本で、現場の人びとに教えを請います。普通に暮らしている人々が言語化していないものを言語化する学問です。人類学に取り組んでみて、知を築き上げているというよりは、わからないことだらけ、というのが今の正直な実感ですね。

大学院生時代。葬儀のフィールドワーク中(写真提供:田中さん)