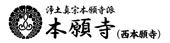お釈迦さまのお墓はどのようなもの?【仏事の疑問】

お釈迦さまのお墓はどのようなもの?
釈尊(しゃくそん)のお墓は、どのようなものだったのですか。
仏教以前のお墓
本題に入る前に、仏教以前のインドで、お墓がどのように考えられていたかをご説明しましょう。インドの古い文献には、たとえば「お墓からの帰り道は、振り返ってはならない」「お墓から帰ったら必ず沐浴しなければならない」「お墓のまわりを左回りにめぐりなさい」といった記述を見ることができます。更に、「お墓が村から見えるところにあると、死がもたらされる」とまで書かれています。このように、墓所(ぼしょ)を、死という不浄なものがある所、避けられるべき所であるとする考え方が、インドには古くからあったのです。
これによく似た考え方が、現代の日本でも見受けられるようです。人間の意識が不思議なくらい変っていないことに、驚かされます。
一方、仏典には、釈尊が墓所で諸行無常の法を説かれたり、行者が墓所で修行を行っていたことが記されています。仏教では、墓所を不浄・不吉なものと考えず、むしろ、生死の意味を学ぶ場としていたのです。
ご遺体への頂礼
釈尊のお墓は仏塔(ぶっとう)と呼ばれています。まずは、この仏塔が建立されるまでの話を見ていきましょう。
釈尊は、四十五年にも及ぶ布教伝道をなされたのち、クシナガラの地で、八十年の生涯を閉じられます。
仏伝によれば、釈尊のご遺体はすぐに火葬されず、十大弟子の一人である摩詞迦葉(まかかしょう)の到着をまって、クシナガラを所領とするマツラ族の手によって荼毘(だび)に付されたようです。摩詞迦葉は、到着するなりご遺体の周囲を右回りに三度めぐり、頂礼(ちょうらい)したと伝えられています。遺体に対する不浄の意識がなかったからこそ、摩詞迦葉は右饒(うにょう)し、崇敬の意を表したと考えられます。
「仏舎利」の原語
さて、釈尊の御遺骨は、「仏舎利(ぶっしゃり)」と呼ばれます。この「舎利」という言葉が「米」の「シャリ」と同じであると言われることがあります。しかし、遺骨の原語はシャリーラ、米の原語はシャーリで、原語は異なります。ただ、漢土(かんど)ではどちらも「舎利」と翻訳される場合があり、混同されるようになったのです。
仏塔と舎利八分伝説
話を元に戻しますが、釈尊が入滅(にゅうめつ)されたという情報は、瞬く間にインド各地に広まり、阿闇世(あじゃせ)の統治するマガダ国を始めとして、七つの部族が仏舎利を求め、クシナガラに参集します。
この時、マツラ族を含む八つの部族は、互いに仏舎利の所有を主張したため、一触即発の状態になったようです。
その時に、一人のバラモンがやってきて、調停役を買って出ます。彼は「釈尊は忍耐のお方であり、慈悲(じひ)をもって私たちを導いてくださった方である。皆は共に和合し、助け合うべきで、仏舎利をめぐって争うべきではない」と言って、舎利を等分することを提案します。諸部族はこの提案を受け入れ、仏舎利を等分します。そして、それぞれの領地に、釈尊のお墓である仏塔を建立し、仏舎利を安置しました。この時、舎利が八つに分割されたので、この出来事は通常「舎利八分伝説」と呼ばれます。
この出来事は、釈尊を慕う人々が国境を超えて広がっていたこと、諸国が仏教を基礎として国を統治しようとしていたことを窺(うかが)わせます。また、当時、緊張関係にあった諸国に対して、仏教教団が宥和(ゆうわ)のメッセージを発していたことが、この物語に反映されたとも、推測されます。
仏塔の供養と仏法
釈尊は生前、「法をよりどころとしなさい」と法の重要性を説き示し、遺体の処理に出家者がかかわらないよう伝えたとされます。
また、『般若経(はんにゃきょう)』には、仏塔を供養することの意義を高く評価しながらも、経典の短い文句を暗誦(あんしょう)することの方が、より高い価値を持つと説かれます。
これらのことは、仏塔の供養にも意義があるが、法が伝わっていくことに、本質的な価値があるということを示していると言えます。
仏塔をめぐる状況
しかし、仏塔の存在と法の伝承が、関わりを持たなかったわけではありません。むしろ仏塔は、在家の信者へと、仏法が広く伝わっていく場であったと考えられます。
在家者のさとりの可能性を積極的に説く大乗(だいじょう)経典は、しばしば仏塔について言及します。例えば「無量寿経(むりょうじゅきょう)』の異訳である『大阿弥陀経(だいあみだきょう)』は、在家者に仏塔の供養を強く奨めています。
こうした経典の記述から、仏塔が仏教信仰の一つの拠点となっており、釈尊を追慕する多くの仏教徒がそこに集まっていたと推測されます。
また『長阿含経』は、仏塔を四つ辻に建てるよう釈尊が指示したと伝えています。四つ辻とは、道と道が交差する交通の要所です。
多くの人が行き交い、偶然そこを通った人々も、仏塔を見上げたことでしょう。
仏塔の周囲をめぐる欄楯(らんじゅん・垣根)には、釈尊の生涯やジャータカ(前世物語)をモチーフとした彫刻が施されています。訪れた人々は、それを見て、釈尊の事跡と遺徳に思いをめぐらし、仏教の精神にも触れたのではないでしょうか。つまり、仏塔は、釈尊の死を悼むだけではなく、釈尊の生涯を通して、法に出遇(であ)える場所だったのです。
仏塔の広がりと墓の意味
インドには現在も、多くの仏塔が残っています。アショーカ王(三世紀)によって建設された有名なサーンチーの仏塔は、最も古いものの一つと考えられています。インドだけではありません。仏教を信仰する国々、タイ、ネパール、中国、韓国……もちろん日本にも、仏塔はあります。日本に現存する最古の仏塔は、法隆寺(ほうりゅうじ)の五重塔(ごじゅうのとう)です。仏教信仰の広まりと共に各地に仏塔が建造され、細分された仏舎利が安置されていったのです。
さて、釈尊のお墓である仏塔は、釈尊の生涯に触れ、その教えに出遇う場所でした。私たちは、こうした釈尊のお墓のあり方を通して、死を不浄とせず、逆に死と対峙(たいじ)し、仏法を学ぶことの大切さを知らされているのではないでしょうか。
教学伝道研究センター常任研究員(現 浄土真宗本願寺派総合研究所 副所長)
藤丸智雄
参考文献
「インド仏塔の研究」杉本卓洲著
画像はイメージです。